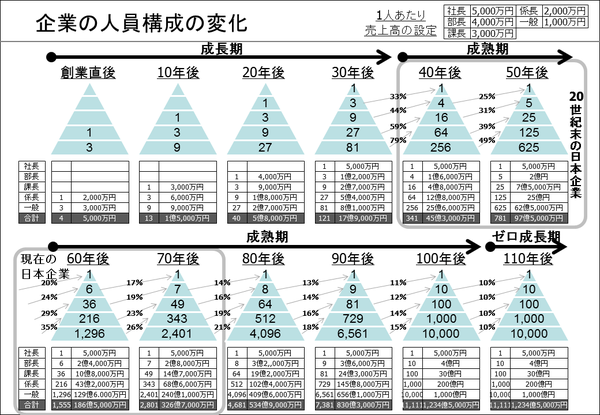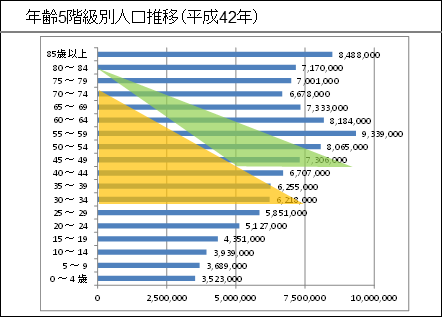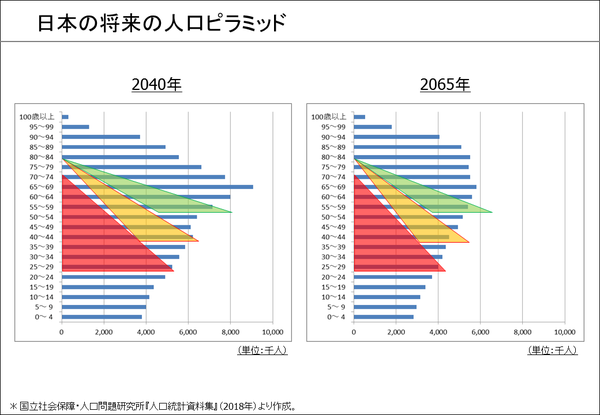2018年09月17日
チャールズ・オライリー、ジェフリー・フェファー『隠れた人材価値』―「価値観重視」の経営は重要だが、ちょっと油断すると簡単に崩壊する
 | 隠れた人材価値 (Harvard Business School Press) チャールズ オライリー ジェフリー フェファー 長谷川 喜一郎 Charles A.,3 O’Reilly 翔泳社 2002-03-20 Amazonで詳しく見る by G-Tools |
伝統的な経営学やコンサルティングファームのアプローチに従えば、まずは戦略を立案する。事業領域を定め、どのような差別化要因で競合他社と戦うのかを決定する。次に、その戦略を分野別の戦略に落とし込む。マーケティング戦略、製造戦略、ファイナンス戦略、人事戦略などといった具合だ。その後、戦略を成功させるためのCSF(Critical Success Factor)を特定する。CSFが特定されたら、そのCSFが反映された社内慣行や制度を整備する。経営陣は、戦略の妥当性や、戦略と各種制度の整合性、施策の遂行状況を見守る。これが伝統的なやり方である。私も以前の記事「【戦略的思考】SWOT分析のやり方についての私見」(戦略立案の外部環境アプローチ)や、「DHBR2017年12月号『GE:変革を続ける経営』―戦略立案の内部環境アプローチ(試案)」で、これらの方法について書いてきた。
本書は、「隠れた人材価値」を引き出すために、「企業や組織の価値観」を中心に据えた経営が重要であることを説いた1冊である。だから、伝統的な経営のやり方とは全く異なる方法を採用する。出発点となるのは、企業や組織の基本的な価値観や信念を定めることである。価値観とは、企業や組織、経営陣や社員が何か重要な意思決定を必要とする局面に直面した時に、判断のよりどころとなる基準である。価値観は社会規範として外部から当然に要求されるものもあるし、当事者がこれまでの仕事・人生経験を通じて主体的に獲得したものもある。通常は、両者がミックスされたものが企業や組織の価値観となる。
次に、価値観に沿って経営慣行を生み出す。人材採用、業績管理、研修や能力開発をどのようなものにするかなどを決定する。その後、コア・コンピタンスを磨く。ゲイリー・ハメル&C・K・プラハラードがコア・コンピタンスという概念を発表した時は、企業や組織の価値観との整合性は特に論じられていなかったように思えるが、ここでは両者の整合性が非常に重要となる。安直な例だが、チャレンジ精神を重要な価値観とする企業は、常にアップデートされる技術の開発能力をコア・コンピタンスとするべきだし、信頼性を重要な価値観とする企業は、徹底した品質管理を通じた高品質の製品の製造能力をコア・コンピタンスとするべきである。
そして、価値観とコア・コンピタンスの連関を出発点として、ここでようやく戦略を立案する。両者の連関を考えた場合、競合他社から模倣されずに価値を生み出すにはどうすればよいのかを検討する。最後に、経営陣の役割は、伝統的には戦略のモニタリングであったのに対し、本書によれは企業文化のマネジメントとなる。そういえば、私も昔のブログでは「競争優位が戦略からビジョンへ移行しつつあることの再発見―『絆の経営(DHBR2012年4月号)』」、「「その課題を解決できるのは自分だけ」という思いが使命感になる―『MBB:思いのマネジメント』(1)|(2)」などといった記事をよく書いていた。私は、両方のアプローチには一長一短があると思う。双方を統合した重厚な戦略論を構築できないものかと思案しているところである。
価値観を中心とした経営が一体どういうものなのかイメージしにくいという方のために、もう少し補足しておく。基本的に、価値観には善悪はない。「人を殺してもよい」というような、よほど極端なものでない限り、ある価値観が成立すると、それとは正反対の価値観も成立する。例えば、ある企業はチームワークを重視するとしよう。しかし、チームワークは普遍的な価値観ではない。というのも、チームワーク重視とは反対に、社員1人1人が自分の力で仕事を完結させる自律性、個の強さを重視するという価値観も成立しうるからだ。
重要なのは、これだと決めた価値観を企業や組織の隅々にまで浸透させることである。これを、日本人が好きな「品質を作り込む」という言葉に倣って、「価値観を練り込む」と表現しよう。チームワーク重視を例にとると、①製品・サービスを提供する社員がチームで顧客の課題解決にあたるように業務プロセスが設計されていること、②場合によっては顧客もチームの一員に加え、顧客と一緒になって製品・サービスを完成させるように案件がマネジメントされていること、③マネジャーは単に部下に対して指揮命令をするのではなく、メンバー間の協業を促し、メンバー間の障害を取り除くことに集中するよう職務が定義されていること、④チーム間で積極的にリソースを融通し合ったり、ノウハウを共有したりすることが認められていること、
⑤チーム間だけでなく、職能が異なる他部門との連携が推奨されていること(マーケティング部門と営業部門、R&D部門と製造部門など)、⑥全ての研修でチームワークの重要性が強調されていること(例えば、必ずグループワークを取り入れるなど)、⑦メンバー同士で相互評価を行わせること、⑧研修や情報システム、予算の企画には現場部門の意見が反映されること、⑨逆に、人事部、情報システム部、経理部は現場部門の業務を十分に理解し、経営資源の適正な配分のために現場業務の見直しを支援すること、⑩他のチームメンバー、他のチームや他部門への貢献が適正に評価される業績・人事評価制度になっていることなどを実現させなければならない。しかも、組織に埋め込まれた価値観には一点の矛盾もあってはならない。
よくありがちなのが、チームワーク重視と言いながら、人事評価は相変わらず個人評価になっているといった例だ。わずかなほころびから価値観に対する社員の信頼は崩壊し、企業の業績を転落させる。価値観を完全に貫徹させられる企業はそれほど多くない。以前の記事「DHBR2018年10月号『競争戦略より大切なこと』―当たり前だが戦略もオペレーションもどちらも重要」で、アメリカでは今、オペレーショナル・エクセレンスが再注目されていると書いた。だが、本当に強い企業とは、単に業務の効率化を図っているだけでなく、価値観を基礎とした完璧な組織をデザインし、それを具現化できている企業のことだと思う。
本書は面白い構成になっていて、そうした価値観重視の経営によって高い業績を上げている7社(サウスウエスト航空、シスコシステムズ、メンズ・ウェアハウス、SASインスティチュート、PSSワールド・メディカル、AES、NUMMI)の事例を紹介した後で、最後に、一見すると価値観重視の経営を取り入れているようでありながら、その取り組みが不十分だったり、あるいは過剰であったりしたがために経営が行き詰まっているサイプレス・セミコンダクターの事例考察が行われている。先ほども書いたように、価値観重視の経営にもデメリットはある。以下では、本書から読み取れる価値観重視の企業の特徴を挙げるととともに、その慣行が不十分だったり行きすぎたりするとどのようなデメリットが生じるかについて整理したいと思う。
まず、価値観重視の経営を行っている企業が最も重視しているのが顧客中心主義である。顧客中心主義ぐらいであれば、今の時代どの企業でも掲げていると思われるかもしれない。しかし、価値観重視の経営を行っている企業のそれは徹底している。サウスウエスト航空の伝説的な顧客サービスについては、今さら私が述べるまでもないだろう。
とはいえ、顧客中心主義が行きすぎると、顧客の「ワガママ」、「モンスター化」につながる。前掲の記事「DHBR2018年10月号『競争戦略より大切なこと』―当たり前だが戦略もオペレーションもどちらも重要」の最後でも書いたが、消費者は自由市場経済の中で勝手に振る舞うことができる私人ではないと私は考える。私人という側面を完全には否定しないものの、消費者は国家から「有限の資源を上手に活用して、社会で賢く生きよ」と命じられている公人でもある。この点を理解しない顧客まで招き入れる必要はない。事実、本書から外れるが、サウスウエスト航空では、カウンターで無理難題を突きつける顧客に対しては、アメリカンエキスプレスのチケットを渡して、「あちらのカウンターに行ってください」と誘導しているようだ。
先ほどから何度か例示しているチームワーク重視も、価値観重視の企業にはよく見られる。目的や機能が異なるチーム同士を協業させることは比較的たやすい。問題は、同じ営業チーム同士や、各地域の製造・販売子会社同士を競わせる場合である。この場合、相手を助けることが自分の業績悪化につながることがあるため、チームワークが発揮されるどころか、逆にお互いの足を引っ張るという事態になりやすい。チームワーク重視を取り入れる場合、自社のビジネスモデルや組織構造がどういう特徴を持っているのかをよく確認する必要がある。また、チームワークを重視する場合、マネジャーはチームメンバーに対して大幅な権限移譲をすることになる。しかし、権力を失うことを恐れるマネジャーが中途半端な権限移譲を行うと、メンバーは自律性が制約される上にマネジャーから干渉を受け、チームが機能不全に陥る。
財務や人事に関する情報を積極的に公開するのも、価値観重視の企業の特徴である。財務情報を公開するのは、社員に対して、自分の仕事がどのように全社の業績とつながっているのかを意識させ、企業に対する貢献意欲を引き出すためである。人事情報を公開するのは、社員が周囲からどう評価されているのか、どんな役割を期待されているのか、自分の強みと弱みは何か、自分の能力を高めるためには何のトレーニングや職務経験が必要とされているのかを理解してもらい、キャリア開発をサポートするためである。
しかし、これらの情報の取り扱いには慎重にならなければならない。まず、情報の公開によって社内競争が巻き起こる恐れがある場合は、情報公開を止めた方がよい。人事情報の公開によって、社員の昇進の順番の予定が公にされた結果、社員同士の足の引っ張り合いに発展するケースもある。もう1つは、情報公開は中途半端に行ってはならないということである。公開するならば可能な限り全てを公開する。公開しないならば公開しないという割り切りが必要である。「この情報は公開してもよいが、あの情報は公開してはならない」というルールを作り始めると、情報公開に関するルールばかりが増えて、経営陣に対する社員の不信感が募る。
価値観重視の企業は、「隠れた人材価値」を引き出すために、人材育成に多大な投資をしている。異動も頻繁に行われる。また、私のように研修サービスを生業としている人間には不利な話なのだが、研修を外注せずに内製化する傾向が強い。私がこんなことを書くと元も子もないのだけれども、研修は内製化できるならば内製化できることに越したことはない。前述のように、研修コンテンツには自社の価値観を十分に埋め込む必要があるし、ブログ別館の記事「ロバート・M・ガニェ他『インストラクショナルデザインの原理』―IDの本なのにこの本自体が全くインストラクティブではなかった」でも書いた通り、研修実施後の業務プロセス、職場環境、評価制度などもセットでデザインしなければならないからだ。外部の研修会社にはこれは難しい。
しかし、単に人材育成に投資しているだけでは、育った優秀な人材をめぐって、異動が頻繁に行われることをいいことに、部門間で仁義なき争奪戦が勃発する可能性がある。それを防ぐには、何のために彼の育成に投資しているのかをはっきりさせなければならない。彼のキャリア志向や特性は何なのか、一方で企業側が彼に期待していることは何なのか、両者を考慮した結果、企業として彼を将来的にどのような方向へと育成していくのか、どんなキャリアパスを想定しているのか、そのために強化すべき彼の強みは何か、逆に彼に欠けている弱みは何か、こうした点を明らかにした上で、強みを伸ばし弱みを克服するためにこのトレーニングを行っているのだという詳細な人材育成計画を立案し、マネジャー間で共有する必要がある。
研修に限らず、価値観重視の企業には自前主義を貫いている企業が多い。例外的にシスコシステムズが買収を通じて成長を遂げているが、同社は買収によって技術を買っているのではない。技術に紐づいている人材を買収しているのであって、彼らに逃げられてしまっては買収は失敗だと言う。だから、綿密なPMIプログラムが用意されており、被買収企業の社員にシスコシステムズの価値観を染み込ませている。買収対象企業をシスコシステムズと完全に一体にしてしまうという点では、自前主義の延長線上にあると言ってもよいだろう。
自前主義は、価値観に基づいた迅速な経営を実現する上でメリットがある。しかし一方で、あまりに価値観が強すぎると、組織が硬直するリスクもある。事業環境が変化しているのに、強すぎる価値観がその変化に関する情報を受けつけないという現象が起きる。これを「過適合」と呼ぶ。先ほど、価値観重視の経営は完璧でなければならないと書いたが、実は、多少穴が開いていた方がよい。それは、価値観に矛盾があってもよいという意味での穴ではなく、異質な価値観を招き入れる余地を残しておくという意味での穴である。
おそらく、この点を最も強く意識している日本企業は、以前の記事「『トヨタが「現場」でずっとくり返してきた言葉』―トヨタの名言とトヨタの弱み」でも書いたように、トヨタであろう。現在、どの業界でも製品・サービスが複雑化しており、1企業が単独で全てのバリューチェーンを担うことは難しくなっている。垂直方向で見れば様々な取引先や販売チャネルと協業し、水平方向で見れば異業種企業や時には競合他社と協業しなければならない局面が増える。
私は旧ブログで、マイケル・ポーターの「価値連鎖(Value Chain)」をもじって、「価値観連鎖(Values Chain)」という言葉を使い、共通する価値観を持つパートナーと組むことが重要だと書いた(旧ブログの記事「自社のビジョンに利害関係者も巻き込む「価値観連鎖(Values Chain)」の再発見―『絆の経営(DHBR2012年4月号)』」を参照)。だが、今はこの考えを改めなければならないと感じている。パートナーはパートナーなりの価値観を持っている。パートナーの価値観を自社の価値観と同質化させるならば、シスコシステムズと変わらない。今後は、パートナーの異質な価値観から学ぶ必要がある。「なるほど、我が社は今までこう考えてきたが、そういう考え方もあるのか」という発見から、新たな創造をしなければならない。
自動車業界の場合、水平方向の関係を見れば、競合他社にエンジンを供給するなど、伝統的に競合他社との連携は盛んである。また、近年はEVの開発をめぐって、異業種との連携も活発になっている。後は、垂直方向の連携をいかに進めるかが問われる。EVが完成すると、今までの部品メーカーとの取引関係はがらりと変わる。また、EVを販売するチャネルも再編されるだろう。新規参入するプレイヤーとどうやって相互学習を行い、顧客に提供する価値に磨きをかけていくのかが、トヨタをはじめとする自動車業界全体の課題である。
価値観重視の企業は基本的に現場を信頼しているため、本社の規模は非常に小さい。本社のスタッフ部門は現場部門の業務プロセスの円滑な遂行を支援し、必要に応じて最適な経営資源を投入することである。だが、権限が小さくなったスタッフ部門がプレゼンスを発揮するために、現場部門に過剰に介入しようとする誘惑に駆られることがある。現場の業務プロセス整備を支援するという名目で、現場業務の複雑さを無視した過度な標準化を行い、分厚いマニュアルを作成して現場部門に使わせる。このリスクを承知している価値観重視の企業では、経営陣が率先してマニュアルやメモの類を廃止している。ところが、今度は権限移譲された現場部門の社員が好き勝手に動いてしまい、無秩序に陥るというリスクがある。
どこまでをマニュアル化し、どこからを社員の裁量に任せるかは非常に難しい問題である。フレデリック・ラルー『ティール組織―マネジメントの常識を覆す次世代型組織の出現』(英治出版、2018年)では、全ての仕事の進め方を社員の自主経営に任せるというやり方が紹介されている。マネジメントは全てインフォーマルなやり方で行われる。だが、日本企業がこれをそのまま取り入れると、ただでさえ暗黙知中心で「重い」と言われる組織がさらに重くなるリスクがあるのではないかと感じる。「組織の<重さ>」に関する研究でも解っていることだが、日本人はフォーマルな手続きがあった方が組織が効率的に回るという。事業や業務の特性、社員の性向に応じてマニュアル化の範囲を決定し、さらにマニュアルの改変を誰がどのような方法で行うのかを明確に決めておかなければならないとしか、今の段階では言えない。
最後に、業績・人事評価についてであるが、価値観重視の企業では、解りやすい業績評価制度が導入されている。また、金銭的報酬でモチベーションを上げることの限界に気づいており、非金銭的報酬を積極的に与える。その最たるものは、「職場の人間関係が良好であること」である。だから、価値観重視の企業は、社員同士の人間関係の向上に常に心を砕いている。このように、金銭的/非金銭的報酬を合わせて、トータルで報酬を設計する。
この点を理解していない企業は、解りやすい業績評価制度を導入しただけでは不安に感じるようである。そもそも業績とは、複合的な要因によって決まる。モチベーションは金銭的報酬によって決まる部分が大きいと考える企業の経営者は、この複合的な要因を解きほぐして、業績を決定づける数式を見つけ出そうとする。その結果、最初は解りやすかった業績評価制度がだんだんと複雑になる。経営陣は、報酬の公平さを実現するためにやっていると主張するのだが、社員はそのように受け取らない。自分の給与が企業にとって都合のよいように操作されていると感じる。すると、経営陣の期待とは裏腹に、社員の間で不公平感が生まれる。
アメリカ人がどう言うか知らないが、個人的には、金銭的報酬は社員が生活費を十分にカバーできるものであれば十分であるし、それ以上はいらないと考える。世の中、お金は揉めごとの原因になりやすい。それを避けるために、経営陣は知恵を絞って非金銭的報酬を多様化し、あの手この手を尽くすことで、社員に「自分はこの会社からこんなにも大事に扱われているのだ。必要とされているのだ」と、企業との絆を感じてもらう方がよっぽど効果的であろう。







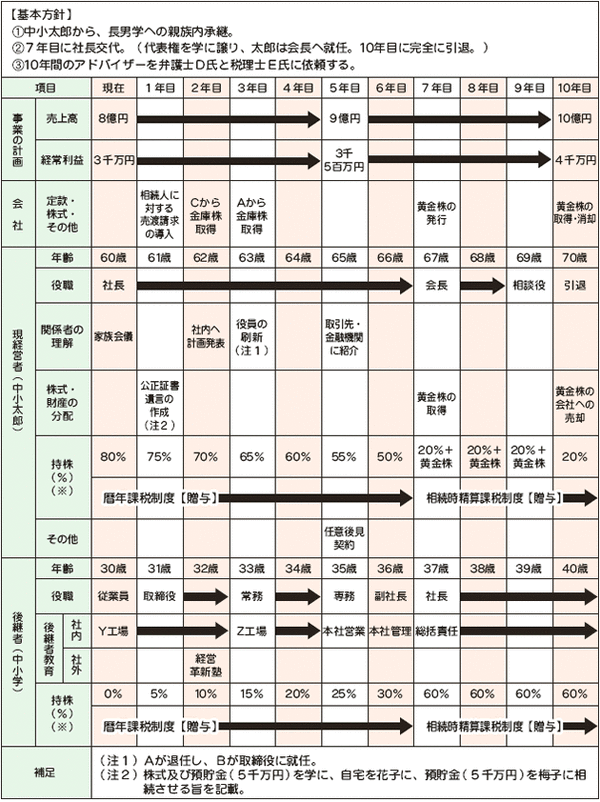
![ダイヤモンドハーバードビジネスレビュー 2018年 2 月号 [雑誌] (課題設定の力)](https://images-fe.ssl-images-amazon.com/images/I/51wC5TV-PWL._SL160_.jpg)