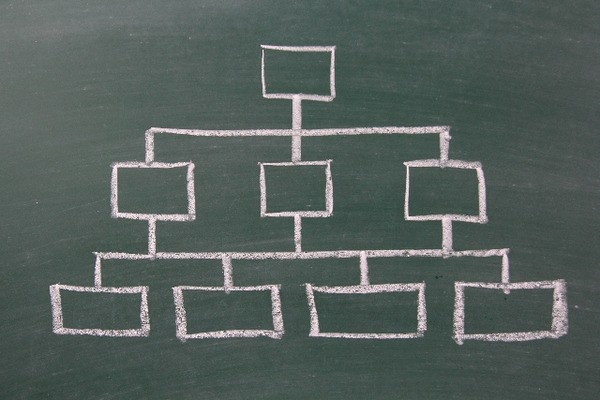2018年09月03日
【中小企業診断士】私が独立診断士として失敗した5つの原因

2011年7月に「オフィス・エボルバー」という屋号で開業し、2013年1月に屋号を現在の「シャイン経営研究所」に変更して、今年で独立診断士として丸7年を迎えた。ただ、2013年7月から2017年2月の3年半あまりは、ある中小企業向け補助金事業の事務局員として、半分会社員みたいな生活を送っていたので、純粋に独立診断士として活動したのは残りの約3年半である。その間、多くの方々に支えていただいたことにはこの場を借りて感謝を申し上げたいが、現時点での私の独立診断士としての活動は「失敗」であると言わざるを得ない。
もちろん、個人事業主といっても1つの事業を営んでいるわけで、それがそんなに短期的に成功するとは思っていない。以前の記事「メラニー・フェネル『自信をもてないあなたへ―自分でできる認知行動療法』―私自身の「最終結論」を修正してみた」でも書いたように、特に私は大器晩成型のようなので、10年~15年程度の長いスパンで物事を見る必要がある。
だが、一方で、別の記事「私の仕事を支える10の価値観(これだけは譲れないというルール)(1)|(2)|(3)」で書いた、「3年で成果が出なければ諦める」という価値観も捨てていない。つまり、最終的な目標は10年~15年後に達成すればよいが、その最終目標に適切に向かっているかどうかを3年ごとにチェックし、中間指標が満足のいくものでなければ撤退するべきだということである。今、私の個人事業は、私が考えていた中間指標の大部分を達成することができなかった。だから、今後の身の処し方を検討しているところである。
昔、「【シリーズ】ベンチャー失敗の教訓」で、前職のコンサルティング&教育研修サービス会社のことを滅多切りにし、「経営コンサルタント出身のくせに自分が経営者になるとまともに経営ができない」などと偉そうに吠えまくっていたことがある。ところが、私自身も経営コンサルタントを名乗っておきながらこのざまなのだから、全くもってお恥ずかしい話である。同じ穴の狢である。「経営コンサルタントというのは、経営のことをろくに知らないいい加減な人間の集まりだ」という世間のイメージに加担してしまったことを罪深く感じる。せめてその罪滅ぼしとして、私が独立診断士として失敗した理由を5つほど整理しておきたいと思う。
(1)夢や目標はあったが志がなかった。
『致知』2018年10月号に「夢や目標はあるけれど、志はあるのか」(河村京子「言い続け、思い続け、やり続ければ、夢は必ず実現する」)という言葉があり、思わずドキッとした。夢や目標というのは、例えば「高級な家に住みたい」、「ベンツに乗りたい」などといった利己的なものである。他方、志とは、人々の役に立ちたい、世の中を変えたいといった利他的なものである。私の場合、20代で前職のベンチャー企業にいた頃から、「30歳でマネジャーになって年収1,000万円を稼ぎたい」と思っていた。しかし、そのベンチャー企業から整理解雇を言い渡されて独立した時には、「35歳には年収1,000万円を達成する」と、夢を先延ばしにした。どちらにしても、夢は夢、利己的なものである。私の場合、整理解雇という憂き目に遭ったので、きっと将来その埋め合わせがあるだろうと、夢の幻影をいつまでも追いかけていたようだ。
もちろん、志が全くなかったわけではない。企業がミッションやビジョンを掲げることの重要性は私自身も繰り返し主張してきたから、自分でも実践していないわけではなかった。シャイン経営研究所のミッションは、「顧客企業の社員を付加価値の高い業務にシフトすることをお手伝いすること」であった。そして、ビジョンとして、「①顧客企業の社員が、1日の業務が終わった時に、『今日はいい仕事をした』と泣いて喜ぶことができるようにすること、②顧客企業の社員が、付加価値の高い業務に見合った報酬を手にすることができるようにすること、③我々(といっても結局7年間で1人も採用しなかったのだが・・・)も、そのような顧客企業の社員とともに仕事ができることを至上の喜びとすること」という3つを掲げていた。
とはいえ、冷静に見つめ直してみると、随分と俗っぽい印象である。歴史学者のアーノルド・トインビーは、「物事の価値を金銭で換算するようになった民族は滅びる」と述べたが、私が掲げたミッションはこれにずっぽりとあてはまっていた。つまり、顧客企業を破滅へと導くミッションだったのである。それに、このミッションは、私の本意を正確に表していない。私は、ピーター・ドラッカーが頻繁に主張していたように、知識労働者がそれぞれ一経営者として仕事をすることを理想としていた。また、キリスト教が伝統的に仕事を悪とするのに対し、石田梅岩が言うように、仕事は人間を成長させるものだととらえていた。だから、私のミッションは、「顧客企業の社員が自社の経営を我がごととしてとらえ、一段高い視点から仕事をするお手伝いをし、社員にとって仕事が人生の重要な意義を持つように支援すること」とするべきであった。
(2)ビジネスモデルが確立していなかった。
恥ずかしい話をすると、私にはビジネスモデルらしいビジネスモデルが長年存在していなかった。経営コンサルタントとしての資質を疑われてもやむを得ない。人事分野という私の強みを活かしたビジネスモデルとして考えられるのは、次のようなものである。まず、ブログ、facebook、人脈などを通じて、私という人間の人となりを知ってもらう。言わば、薄いファンを作る。次に、Webサイトで無料の「経営力診断」を提供し、私が経営全般に関して一定の知見を有する人間であることを訴求して、潜在顧客のプールを形成する。
その中で、自社の組織風土に関心がある企業に対しては、まずはWeb上で無料の「組織風土診断」(簡易版)を受けてもらい、さらに突っ込んだ調査を希望する企業には、有償で詳細な「組織風土診断」を受診してもらう。その結果、「人事制度に不満を持っている社員が多い」、「将来のキャリアが見えない」という回答が多ければ、「人事制度の再構築」、「セルフ・キャリアドックの導入」というハード面のソリューションを提供する。「上司の部下マネジメント力が弱い」、「戦略に納得していない」という回答が多ければ、「部下マネジメント研修」、「創発的戦略構築研修」というソフト面のソリューションを提供する。そして、そこから継続フォローにつなげていく。実は、こういうビジネスモデルを思いついたのは、今年に入ってからである。
ここまではっきりしたビジネスモデルを描かなくても、顧問契約を獲得するためのパターンをもっと早い時期に確立するべきであった。例えば、私が考えた1年間のモデル顧問契約サービスは次の通りである。最初の3か月は環境分析を行い、望ましい戦略を導き出して、戦略を実現するためのビジネスプロセスを詳細化する。そして、業務の改廃や組織の統廃合、職務の再定義などを行い、新しい職務分掌や業務マニュアルを整備する。
次の3か月は、新しい業務プロセスを遂行するにあたって必要となる新しい知識や能力を習得するための人材育成計画を策定し、研修を実施する。その次の3か月は、研修で学習し、現場で実践したことが適切に評価される人事制度を構築する。最後の3か月は、新しい業務プロセスを下支えし、現場での学習を促進し、公正な人的資源管理を行うためのITを導入する。そして契約更新後は再び環境分析を行い、戦略をブラッシュアップする。こうした形で、私の強みである戦略立案、人材育成、人事制度構築、IT導入をフルに動員した顧問契約サービスを設計することは可能であった。このパターンを思いついたのも去年ぐらいである。結局、7年間で顧問契約は1社も獲得できなかった。私が従事したのは全てスポット案件である。
ビジネスモデルが曖昧だったので、ターゲット顧客も非常にあやふやであった。言い換えれば、上記のビジネスモデルがぴったりとあてはまる中小企業に的を絞ることができなかった。上記のビジネスモデルはいずれも人事制度の構築を含んでいる。中小企業で人事制度が本格的に必要となる、また既に人事制度を導入済みでもその制度に課題が生じ始めるのは、だいたい社員数が50~100人を超えたあたりからである。社長が1人で全社員の評価をつけるのに限界が来るためだ。それなのに、私は頼まれるがままに、小規模企業やまだ売上が立っていないベンチャー企業のコンサルティングをかなりやっていた。
顧客企業の規模がバラバラであることに加えて、引き受けた仕事の種類もバラバラであった。「若いうちは何でも勉強だ」と言い聞かせて、いただける仕事には何にでも手を出してしまった。もちろん、仕事が自然と多角化することはある。私の先輩の独立診断士は飲食店に強いことをずっと売りにしていたところ、いつの頃からかそこから派生して、他の業界からも仕事をいただけるようになったと話していた。しかし、これは例えるならば、ボウリングでセンターピンがしっかりと立っていて、センターピンにボールが当たった結果、他のピンも倒れたようなものである。私の場合は、確固たるセンターピンがないのに、ふらふらと色々な仕事を彷徨い歩いていた。海外勤務の経験がない私が、海外企業の信用調査をしたり、海外事業のリスクマネジメントの仕事をしたりしたのは、今となっては意味不明である(それはそれで勉強にはなったが)。
(3)他の診断士からの紹介に頼りすぎた。
以前の記事「中小企業診断士を取った理由、診断士として独立した理由(6)【独立5周年企画】」で書いたように、他の診断士から仕事を紹介してもらうことは大切である。ただ、私の場合は、それに味を占めて、診断士からの紹介案件に依存しすぎてしまった。これは事業としては危険である。仕事を依頼する側の立場に立てば解るのだが、彼らが私のような人間に仕事を依頼するのは、その仕事が自分の手に負えないから、あるいは収益性が低いからであることが少なくない。自分でできるならば、あるいは収益が高いならば、わざわざ他人に紹介しようとは思わない。彼らとて自分で食っていかなければならない。もちろん、中には善意でいい仕事を紹介してくれる方もいる。しかし、残念ながら全員がそういうタイプとは限らない。
さらに悪いことに、私は案件の収益性を計算するのが苦手である。この案件が収益につながるのか、仮に短期的には利益が出なくても、将来的に案件が成長してリターンが見込めるのかを予測する能力が欠けている。だから、生活に支障が出る(と後で解る)レベルの安い案件でも引き受けてしまう。この点については、以前の記事「加藤諦三『どうしても「許せない」人』―自己蔑視する人は他人にいいように利用される(実体験より)」でも触れた。
それで大失敗をした例が以前の記事「『致知』2018年4月号『本気 本腰 本物』―「悪い顧客につかまって900万円の損失を出した」ことを「赦す」という話」で書いた話である。実は、これ以外にもやらかしている案件がいくつもある。私が勝手に計算しただけにすぎないものの、潜在的な損失は2015年以降だけで1,500万円を超えていると思う。さらにつけ加えると、こういう危ない案件に携わった他のメンバーは、途中で上手に案件から逃げ出していることが多い。私はリスク感性が鈍いせいか、最後まで案件に携わってしまう。そして、案件が終わってから、いただいた報酬の少なさに慌てるのである。稲盛和夫氏は「経営とは値決めである」と言っていたのに、私は値決めができなかった。つまり、経営ができていなかった。
マーケティングにおいても、紹介によって仕事を獲得することは重要であるとされる。顧客獲得コストを大幅に節約することができるからだ。しかし、その紹介元が同業他社であるというのはあまりよくない。大企業の創業者の本を読んでいると、「競合他社ができないと音を上げた難しい仕事を引き受けて、それを何とかやりきることで社員のモチベーションを上げた」というエピソードがよく出てくる。しかし、私はこの手法はそうそう頻繁には使えないと思う。競合他社と自社の間には利害関係がある。だから、競合他社にしてみれば、収益性の悪い面倒な仕事を押しつけて相手を苦しめてやろうという心理が働かないとは言い切れない。
いい紹介とは、顧客からしてもらうものである。顧客から、その顧客とは利害関係のない別の顧客を紹介してもらう。その顧客が仲良くしている企業のことだから、企業規模も、経営者のものの考え方も、収益力も、組織風土も似ているだろう。こういう顧客を紹介されれば、案件の収益面で苦しめられるリスクは少なくなる。私の場合、顧客企業から別の顧客企業を紹介してもらったことがないのが痛かった。顧客企業に対して、「同じように困っている企業さんをご存じではないですか?」と聞けばよいだけだったのに、それすらしなかった。
(4)常に特定顧客への依存度が30%を超えていた。
中小の下請企業の場合、大口顧客への依存度が30%を超えていると危険であると言われる。容易に想像がつくことだが、大口顧客からの受注が消えた瞬間、売上高が30%も落ち込む。だから、顧客はできるだけ多角化して、ポートフォリオ管理するのが経営の定石である。にもかかわらず、私は確たるビジネスモデルも持たず、明確なターゲット顧客に対して営業活動をせず、他の診断士から紹介されるがままにスポット案件ばかりやっていたので、ほとんど常に特定顧客への依存度が30%を超えていた。30%どころか、70~80%ぐらいだったことも珍しくなかった。1つの案件が終わると売上高が急激に下がる。そこで慌てて目の前にある紹介案件に、収益性をよく考えずに飛びついてしまう。この繰り返しだった。
仮に明確なターゲット顧客とビジネスモデルを持っていたとしても、特定顧客への依存度が30%を超えることはある。例えば、同じ顧問料を払ってくれる顧客企業が3社しかなければ、特定顧客への依存度は30%を超える。これも私の悪い癖なのだが、1つの案件をほとんど1人でやろうとしてしまう。他のメンバーと一緒に仕事をしても、前述のように途中でいなくなることが少なくない。こうした問題を回避するためには、私が案件の収益性を適切に見積もることができることを前提として、仕事を分担することができる緊密なパートナーを見つけるべきだったと考える。そうすれば、私はもっと多くの顧客・案件を一度に抱えることが可能だっただろう(パートナーもまた、同様に多くの顧客・案件を一度に抱えることができる)。仮にいずれかの案件が終了したり、途中でダメになったりした場合でも、その影響はある程度抑えられる。
その際、決して、仕事をパートナーに丸投げしたと思われないようにしなければならない。私が自分の得にならない仕事をパートナーに押しつけたと受け取られる恐れがある。また、パートナーは数が多ければよいというものでもない。パートナーの数が増えれば、必然的にそれぞれのパートナーに行き渡る仕事の量が減る。それは、パートナーの暮らしを不安定にする。私は、たくさんのパートナーを使って、自分は上前だけはねるビジネスをやっている診断士にも会ったことがある。このモデルだけは絶対に真似してはならないと感じた。
(5)気分転換の機会を作らなかった。
会社勤めであれば、基本的に土日は休みでなる(もっとも、土日も働かせるブラック企業はある)。しかし、独立して1人で仕事をしていると、自分で意識しない限り、休みを確保することができない。私は2012年の夏に一度倒れて入院し、2013年の中盤までは週3日ぐらいのペースで仕事をして、顧客をゼロから再開拓しつつ仕事のリズムを取り戻すことに専念していたのだものの、2014年から仕事が増え、2015年からはとうとう休みがなくなった。2012年、2013年と満足に仕事ができなかった分を取り戻そうという思いもあった。
本ブログで告白しているように、私は2008年秋から双極性障害という精神疾患を患っている。2015年~2017年はたまたま薬のコントロールがある程度上手くいっていた時期で、絶好調というわけではなかったものの、ずっと仕事をしていた。放っておくと歯止めが効かないのも私の悪い癖である。朝5時頃に起きてメールのチェックから仕事を始め、夜は19時~20時まで働き、仕事の合間を縫って年間約200冊の本を読み、約60万字分のブログを書き、残りはほとんど寝ていた(私は抑うつ時に過眠傾向になる)。病気の影響により仕事の途中でこまめに休憩を取る必要があるため、1日の仕事時間は合算で8~9時間であった。とはいえ、週6.5日のペースで仕事をしていたから、年間の労働時間は3,000時間(=8.5時間×6.5日×52週)近くになっていた。ここに、読書の時間(1冊3.5時間として750時間)とブログの時間(私は1時間で2,000字書くので、年間300時間)を加えれば、年間の活動時間は約4,000時間となる。
読書とブログは私の趣味みたいなものだから除外するとしても、それでも年間3,000時間労働は度を越えているだろう。これでは1人ブラック企業である。我ながらよく死ななかったと思う。一応、睡眠時間は確保できていたことが幸いしたのかもしれない。今年の3月に入院する際には、かかりつけの医師からは過労だと言われた。私の場合、単なる過労ではなく、精神障害も重なっていたから、3月の1回の入院では十分に回復せず、4月に働き始めたのも束の間、7月には再び3週間実家で自宅静養することになってしまった。2012年に倒れた時もそうだったように、一旦仕事に穴を開けると、一気に顧客を失う。そして、復帰後はゼロからの再出発になる。今年は2度倒れているため、事業の継続性にいよいよ黄信号が灯るようになった。
「心技体」という言葉があるが、私は「体心技」ではないかと思う。仕事をする上でまず何よりも大切なのは、身体が健康なことである。その次に来るのが精神、最後に来るのが技術・知識・能力である。世の中で評価されるのは、優秀な人間よりも体力のある人間である。次点が精神的に健康な人間だ。企業などで出世していく人を見ればこのことはよく解る。だから、身体と精神の健康を保つために、意識的に休息を取らなければならない。私は技術・知識・能力の向上に全振りした結果、身体と精神を損なって、社会のルールを踏み外してしまった。