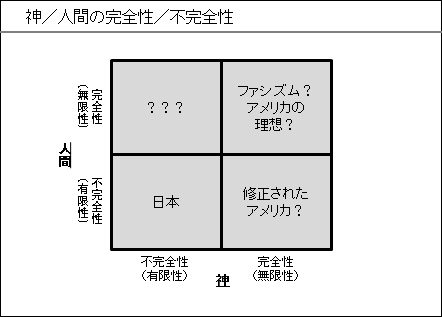2018年01月05日
神崎繁『フーコー―他のように考え、そして生きるために』―「疎遠なるもの」に自己を変容させて到達する姿勢を経営学にも適用できるか?
 | フーコー―他のように考え、そして生きるために (シリーズ・哲学のエッセンス) 神崎 繁 日本放送出版協会 2006-03 Amazonで詳しく見る by G-Tools |
最初にこの本を読んだ時は全く理解できなくて、別のフーコー入門書を2冊読んだ後にもう一度チャレンジしたのだが、やはり十分には理解できなかった。120ページぐらいの薄い本なのに、デカルト、カント、ヒューム、サルトル、ハイデガー、フッサール、ニーチェ、メルロ=ポンティ、デリダなど様々な哲学者が登場するため、予備知識に乏しい私にはハードルが高かった。それでも、私なりに整理できたことを記事にしてみたいと思う。
《参考記事(ブログ別館)》
重田園江『ミシェル・フーコー―近代を裏から読む』―近代の「規律」は啓蒙主義を介して全体主義と隣り合わせ
中山元『フーコー入門』―「生―権力」は<悪い種>だけでなく<よい種>も抹殺してしまう
我々が外界の事物をどのように認識するかについて、哲学者がどう考えたかについて見ていきたい。まずはデカルトである。デカルトは方法的懐疑という手法を用いて、あらゆる認識を疑った。そして、疑っているという自分が存在することだけは疑いようのない事実であることから、かの有名な「われ思う、ゆえにわれあり」という言葉を導き出した。
デカルトは啓蒙主義の先駆けである。啓蒙主義とは、端的に言えば理性を絶対視する立場であり、先ほどのデカルトの言葉はこれをよく表している。その理性に対して、外界の事物はストレートに飛び込んでくる。理性が事物を表象する時、理性の中に埋め込まれた観念を組み合わせてイメージを形成する。逆に言えば、あらゆる事物は必ずいくつかの基本的な観念に分解できるということである(要素還元主義)。ここで、あらゆる事物の原因となる基本的な観念はどこから来たのかという問題が生じるが、デカルトはそれは神が仕込んだのだと答える。これがデカルトによる神の存在証明である。神がインプットした観念を組み合わせて表象するのだから、誰が(どの理性が)事物を表象しても、必ず同じようにイメージされる(以前の記事「斎藤慶典『デカルト―「われ思う」のは誰か』―デカルトに「全体主義」の香りを感じる」を参照)。
デカルトの哲学が経験主義を下地とした唯物論であるのに対し、カントの立場は観念論と呼ばれる。デカルトは理性を絶対視したが、カントは経験や理性の限界を認める。デカルトにおいては、事物の無限な観念を人間の理性が持つことの根拠として神の存在が前提とされた。他方、カントにおいては、一方で理性が自らの経験の限界を設定することで自ら従うべき法則を課す自律性を確保しながら、同時にそうした経験を可能にする根拠を自らのうちに持つ必要が生じた。デカルトは認識の主体である身体や感覚まで方法的懐疑によって退けてしまったが、カントは認識の主体である人間を必要とした。そしてこの人間は、事象を見るのと同時に、自分自身を見ている。ただ、限定された理性が対象を見ていると同時に、自分自身も見られているという時の表象が各人にとってどんなものなのか、私もこの文章を書きながらよく理解できていない(汗)。
デカルトもカントも、外界の事物が理性に飛び込んでくるという点では共通していたが、フッサールはこれとは異なる見解を示した。フッサールは、理性の方が外界の事物に向かって働きかけるというもう1つの矢印を想定した。フッサールは文の成立過程について考察を行っている。例えば私がペンを見た時、まずは「知覚の志向性」が働く。ペンの一部を見て、おそらくこれはペンであろうという認識を持つ(この段階ではまだ文にはなっていない)。部分的な経験から事物全体へと向かうことを可能にするものを、フッサールは「質料」と呼ぶ。次に、「これはペンである(これはペンであれかし)」という「信念の志向性」が現れる。そして最後に、「これはペンである」という文が発せられる(以前の記事「門脇俊介『フッサール―心は世界にどうつながっているのか』―フレーゲとフッサールの違いを中心に」を参照)。
外界の事物がストレートに理性に飛び込んでくるという点をもっと深く掘り下げたのがメルロ=ポンティとサルトルである。メルロ=ポンティは、外界の世界も意味を持ち、それを再分配するのだと言う。ある時、私が森の中を通って海岸まで通じる道を歩いていたとする。私の周りの木々はどれも真っ直ぐに伸びている。だが、遠方に1本だけ、幹が斜めになり、葉の色が変色しているように見える木がある。おそらく枯れ木だろうと私は考える。しかし、私が海岸に近づくにつれて、枯れ木のように見えていたものが、実は随分昔に座礁した難破船であることが解った。
通常は、私が最初に難破船を枯れ木と見間違ったのは、私の記憶の中に、私が今まで見てきた枯れ木の映像があり、私が見たものがそれと合致したからだと考える。その見解を改めたのは、私が海岸に近づくにつれ、船のマストらしきものが見え、幹に見えたものが船の先端であったことに気づいたからである。こうして部分的な情報を総合した結果、枯れ木に見えたものが実は難破船だったと判断することになる。ところが、メルロ=ポンティはここで「ゲシュタルト」の概念を持ち出す。ゲシュタルトにおいては、全体は要素の総和ではなく、むしろ各要素の感覚的な値自体が、全体におけるその機能によって規定されており、また、その機能とともに変化する。
私が枯れ木から難破船へと認識を改めるのは、部分の知覚が総合へと至るからではない。個々の部分が連合され、全体の意味が再構築されるのではない。風景の全体が変容することで、部分の知覚が意味を変える。全体から部分へと意味が再分配されて、全体の意味とともに部分の意味が共変する。連合ではなく、配分が問題なのであり、ここにおいて「世界の相貌」が一変する。これを私なりに解釈すれば、私が風景に対して意味を与えるのではなく、風景自体が全体として意味を持っており、それが時に応じて部分に対して意味を再分配する、ということである。そして、メルロ=ポンティは、意味が流れ出る現場に立ち会う必要があると述べている(以前の記事「熊野純彦『メルロ=ポンティ―哲学者は詩人でありうるか?』―意味は「感覚されるもの」と「感覚する者」の「交流」によって生まれる」を参照)。
サルトルは、「眼差し」について考察を行っている。他者への眼差しは、その他者を対象化することによって、本来それ自体も「対自存在」、つまり意識的存在として自由なあり方をしているはずの他者を「即自存在」、すなわち事物と変わらない扱いをすることになる。だが、このことは翻って自己自身にも現に生じていることであり、眺めているということは、眺められているということを意味する。こうして、サルトルは、自己の自由というあり方が、他者の眼差しによって不意打ちを受けて逆転することから生じる疎外感や羞恥心を、自己の本質的構成要件と考える。つまり、自己は本質的に「対他存在」である(サルトルの主張も私はまだよく理解できていない)。
さて、理性との関係でもう1つ問題になるのが、感情の位置づけである。伝統的なストア派は、理性と感情は対立しないという立場をとった。フーコーは(ここでやっとフーコーが出てきた)、デカルトが理性から狂気を排除していると指摘する。だが、デリダは逆に、デカルトは理性から狂気を排除していないと主張をしており、2人の間で論争が繰り広げられている。デカルトにおける感情の扱いが揺れるのは、『情念論』では理性と感情が両立するかのように書かれているのに対し、『省察』では理性から感情が排除されているかのように記述されているためである。
フーコーは、死、狂気、逸脱、異常といった限界概念を経験の基点とした。自らに疎遠なものに敢えて挑んで自らのものとする、しかも自らを変えずに疎遠なるものを同化するのではなく、自らの変容を通じて、どこまで到達し得るかという限界を見極めようとした哲学者であった。
私は、経営学やビジネスの現場で用いられる理論が、近代哲学を後追いしていると感じる時がある。例えば、ロジカルシンキングでお馴染みのMECE(Mutually Exclusive and Collectively Exhaustive:漏れなく、ダブりなく)とは、ニュートンやデカルトの言う要素還元主義のことである。カリスマ的な強いリーダーシップによって組織の価値観を統一し、変革を進めるという手法は、唯物論的な世界観を前提としている。また、意思決定の局面においては、まずは考え得る選択肢を全て洗い出し、冷静に時間をかけて検討を行えば必ず最善の解に行き着くと信じられているが、これはまさに啓蒙主義時代の代表的な考え方そのものである。
しかし、社会は企業活動だけで成立しているわけではない。企業活動の上には政治が乗っている。そして、政治とは権謀術数の世界である。そこでは褒め殺し、誘惑、媚び諂い、威嚇、恫喝、脅迫、取引などが日々行われている。啓蒙主義が理想とした世界からはほど遠く、とても合理的な意思決定が行われているとは思えない。こうした政治の世界については、マーティ・リンスキー、ロナルド・A・ハイフェッツの『最前線のリーダーシップ』(ファーストプレス、2007年)が詳しい。また、以前には、公務員改革をめぐって「長谷川幸洋『官僚との死闘700日』―抵抗勢力の常套手段10(その1~3)|(その4~7)|(その8~10)」という記事を書いたこともある。
 | 最前線のリーダーシップ マーティ・リンスキー ロナルド・A・ハイフェッツ 竹中 平蔵 ファーストプレス 2007-11-08 Amazonで詳しく見る by G-Tools |
政治の世界とは、人間精神の異常が前面に出てくる世界である。啓蒙主義者は認めたくないだろうが、政治の世界がこのように混乱していても、国家は何とか回っている。ということは、啓蒙主義者が考える合理的な意思決定よりも、現実の政治的な意思決定の方が本質に近いのかもしれない。そして、こうした政治世界の傾向は、企業活動にも及びつつあると感じる。従来の企業活動は経済的、量的であったため、近代的な算術で処理することができた。だが、これからの企業は社会的ニーズと多様なステークホルダーに対応する質的な経営が求められる。換言すれば、企業活動が政治化する。ということは、フーコーのように異常からアプローチする必要が生じるに違いない。ここにおいて経営学は、現代哲学に追いつく。これは一見受け入れがたいことだが、我々は「イノベーションは辺境から生じる」というあの格言をここで思い出す必要がある。