2017年02月12日
日本企業が陥りやすい10の罠・弱点(1/2)
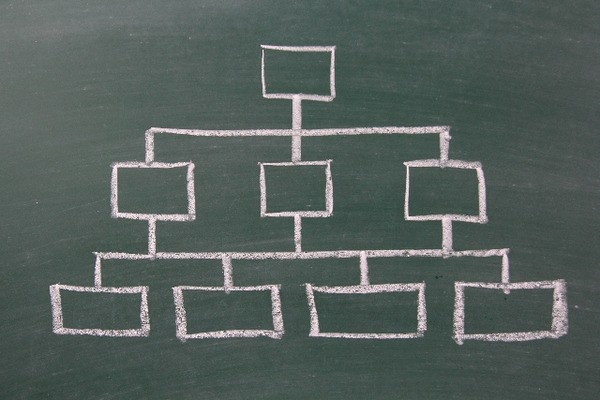
以前の記事「『一生一事一貫(『致知』2016年2月号)』―日本人は垂直、水平、時間の3軸で他者とつながる、他」、「山本七平『日本はなぜ敗れるのか―敗因21ヵ条』―日本組織の強みが弱みに転ずる時(1)|(2)」でも書いたが、日本社会は全体が巨大なピラミッド構造であり、垂直、水平、時間の3軸で緊密につながっている。垂直方向のつながりを見てみると、上の階層は下の階層に単に命令するだけでなく、下の階層の人々に対して、「あなたたちの目的を達成するために私に何かできることはないか?」と「下問」する。また、下の階層も単に上の階層の指示に従うだけでなく、「もっとこうした方がよい」と「下剋上」する(通常の下剋上の意味とは異なり、ここで言う「下剋上」は上の階層の排除を目的としない。下の階層はその階層にとどまったまま「下剋上」をし、上の階層は「君がそこまで言うなら自分でやってみなさい」と権限移譲する)。
水平方向には「コラボレーション」が見られる。欧米に比べて、日本の組織では部門・職種を超えたジョブローテーションが盛んに行われる。個人の水平的な能力開発を促すと同時に、部門間の連携を強化するのが目的である。また、日本組織は外部との連携も強い。アメリカの業界団体がロビー活動を主目的としているのに対し、日本の業界団体は、同業者の間で自社の戦略や製品・サービス、技術などについて情報交換をするのが目的である。そうした交流から、時にライバル同士が手を組むこともある。アメリカ企業は、「自社で何でもできる」という優越感から、自前主義に走る傾向が強い。一方、日本企業は「自社の資源は限られている」という認識を持っている。そこで、自社に足りないリソースを調達するために、時に異業種とも積極的に連携する。
日本組織は時間軸も重視する。現在は過去の重層的な経験の上に成り立つ。よって、改革によって組織全体を抜本的に変えるよりも、伝統に接ぎ木をすることで漸次的に組織を進化させる方を好む。もちろん、進化によって結果的に組織が大幅に変わることはある。だが、最初から改革を目的とするのではない。無限の改善の先に大きな改革が実現されると考える。こうした日本組織の歴史重視の姿勢を知らずに、欧米流の変革マネジメントを導入すると失敗する。以上が日本組織の大まかな理想である。しかし、こうした理想が崩れると、途端に弱みが露呈する。今回の記事では、企業に限定した話になるが、日本企業が抱える10のリスクをまとめてみた。
①階層構造が崩れるとリンチが出現する。
日本社会は多重階層構造である。組織が多重化していると、情報が上から下(あるいはその逆)に流れるのに時間がかかり非効率だと考えられるのが一般的である。ところが、日本の場合は、この多重階層構造を死守しなければならない。というのも、この構造が崩れて社会がフラット化した瞬間、秩序が崩壊し、リンチが出現するからである。山本七平は日本陸軍でそのような経験をしたと語っている(以前の記事「山本七平『日本はなぜ敗れるのか―敗因21ヵ条』―日本組織の強みが弱みに転ずる時(1)|(2)」を参照)。
戦中・戦後ほどの強烈な体験ではないが、私もこのリンチ構造には思い当たる節がある。私は前職で外資系コンサルティングファームの出身者と随分と仕事をした。たいていの外資系コンサルファームは組織がフラット化している。こうした企業で起きているのは、上位者による下位者(若手コンサルタント)のリンチである。具体的には、「頭が悪いんじゃないか?」、「お前は全く使えない」、「死んだ方がましだ」などと延々と罵声を浴びせ、他人が見ている前で部下が作成したパワーポイントの資料を破り捨てる。そして、連日徹夜で作業をさせ、2、3年経って部下が疲弊した頃にポイ捨てするのである(もちろん、これが全てではないが)。組織がフラット化すると、上位者が持つ権限が大きくなる。日本人はそれを暴力的に行使してしまう。
現在、国会では憲法改正が争点となっている。国民が理解しやすい「緊急事態条項」を入れるという案が挙がっているそうだが、個人的にはこの条項は止めておいた方がよいと思う。緊急事態条項とは、要するに大規模災害などの緊急事態時には、内閣に権限を集中させ、日本全体をフラット化するというものである。だが、その後に起きるのは、おそらく内閣による地方自治体のリンチであると私は予想する。緊急事態においては迅速な意思決定が求められるものの、それでも私は日本の多重階層構造をできるだけ維持すべきだと考える。
②顧客に共感しすぎて顧客を誤解する
アメリカからは、顧客のニーズをよりよく理解するための手法として、ペルソナ・マーケティングやエスノグラフィー・マーケティングなどが輸入されてきた。また、P&Gの"Livin' It"(P&Gの社員が消費者の自宅で一定期間生活をともにすることで、消費者のニーズを探るというプログラム)といった事例が紹介された。ところが、これらのことは、実は日本企業が昔からやっていたことである。日本の消費者は世界一注文が多いと言われる。その”難しい”顧客を理解するために、日本企業は顧客の声に常に耳を傾け、顧客の行動をつぶさに観察してきた。
端的に言えば、日本企業は顧客に共感するのが上手だということである。ところが、ここで1つ警告をしておかなければならないことがある。あまりに相手に共感しすぎると、相手の本心を誤解するリスクがあるという点である。以前の記事「『組織の本音(DHBR2016年7月号)』―イノベーションにおける二項対立、他」で、フォードが開発した「エンパシー・ベリー」という、妊婦の痛みなどを疑似体験できる装置について触れた。男性が妊婦のことを理解するために開発されたものであるが、疑似体験がリアルすぎると、かえって妊婦に対する誤解を助長する恐れがあると指摘されている。日本企業も、顧客に接近するのはよいが、接近しすぎるのは問題である。
③顧客を思いやるあまり、顧客に対してウソをつく
心理学には「セルフモニタリング」という用語がある。セルフモニタリングが高い人はその場の状況に応じて言動を変える傾向が強く、逆に低い人は一貫した言動をとりやすい。セルフモニタリングが高い人ほど出世しやすいことも解っている。そして、研究によれば、日本は典型的なセルフモニタリング社会なのだという。常に他者のことを思って柔軟に行動するからであろう。ただし、セルフモニタリングが高いことには問題もある。他者のことを思うあまり、他者に正しい情報を提供せず、自己を正当化する傾向が強いのである。「この情報を顧客に伝えると、顧客が不安に思うかもしれない」―こういう心理が、品質問題の隠蔽などにつながる。
通常、他者との関係を大切にするならば、客観的な情報を誠実に伝達することを重視するはずである。ところが、日本人は他者との関係を大切にするあまり、客観的な情報を曲げてしまう。企業がそういう態度を取る可能性があることを顧客が知ると、顧客は「あの企業は何か重要な情報を隠しているのではないか?」と不安になる。それが過熱すれば、「あの企業の製品・サービスには何か欠陥があるに違いない」という疑惑に変わる。本当は何の欠陥もないのに、悪評だけが口コミによって市場に伝播する。これが「風評被害」のメカニズムである。実は、風評被害という言葉は日本にだけ存在し、英語にもロシア語にも翻訳できないそうだ。
④顧客のニーズはこうだと勝手に思い込む
②では、日本企業が顧客に接近しすぎることを問題視したが、逆に顧客との距離が遠すぎるのも問題である。以前の記事「【シリーズ】現代アメリカ企業戦略論」でも書いたが、アメリカ企業はイノベーションに強い。イノベーションとは、ニーズを先取りするものであるから、伝統的な市場調査が通用しない。そこで、イノベーターは自分自身を最初の顧客に見立て、「自分だったらこういう製品・サービスがほしい」というものを形にする。そして、「自分がこれだけほしがっているものは、世界中の人もほしがるに違いない」と考えて、イノベーションを全世界に普及させる。もちろん、大部分のイノベーションは失敗に終わるのだが、アメリカ人の中には唯一絶対の神に選ばれた人がいて、彼が神と正しい契約を結ぶことができれば、そのイノベーションは成功する。
日本企業はアメリカ企業の真似をしようとするが、残念ながら多神教文化に生きる日本人には、一神教文化が想定するような傑出した能力を持つ人はいない。日本人は平均的に優秀であるものの、多神教の神と同じくどこか不完全な部分を抱えているというのが前提で、飛び抜けた人材はいないのである(これは、抜群にIQが高い人にアメリカ人が多く、日本人は少ないという事実が示している)。だから、アメリカ流のイノベーションを起こすのはほぼ不可能だ。日本企業は、顕在化したニーズを丁寧に拾い上げて、それを製品・サービスにきめ細かく反映させていくというマーケティングの王道を歩むしかない。間違っても、例えば練馬区の商店街で外国人向けに練馬ダイコンを売ればよいなどと直感的に判断してはいけない(以前の記事「中小企業診断士が「臨在感的把握」で商店街支援をするとこうなる、という体験記」を参照)。
(続く)
カテゴリ:
経営





