2016年08月29日
【ドラッカー書評(再)】『新しい現実』―「計画上は失敗だが、実際には成功した」という状態を目指せ、他
![[新訳]新しい現実 政治、経済、ビジネス、社会、世界観はどう変わるか (ドラッカー選書)](http://ecx.images-amazon.com/images/I/415RQXGQKXL._SL160_.jpg) | [新訳]新しい現実 政治、経済、ビジネス、社会、世界観はどう変わるか (ドラッカー選書) P.F.ドラッカー 上田 惇生 ダイヤモンド社 2004-01-08 Amazonで詳しく見る by G-Tools |
(前回の続き)
(4)以前の記事「『腹中書あり(『致知』2016年7月号)』―私の腹中の書3冊(+1冊)」で、ドラッカーは組織のフラット化には否定的である一方で、分権化は推し進めるべきだと主張しており、日本の組織の考え方と親和性が高いと書いた。だが、本書では、情報社会の進展によって組織の階層が著しく減少すると述べられている箇所があった。
データ処理能力を情報力の向上に向けたとき、組織の構造に影響が出てくる。ほとんど瞬時にして、マネジメントの階層と経営管理者の数を大幅に減らせることが明らかになる。そもそもマネジメントの階層の多くが、意思決定の役に立っていないことが明らかになる。ドラッカーが分権化を強調したのは、トップマネジメントの候補であるミドルマネジメントに大きな権限と責任を与え、トップマネジメントに必要な資質を訓練するとともに、誰が次のトップマネジメントにふさわしいか評価をするためであった。ところが、組織がフラット化すると、ミドルマネジメントの訓練の機会が大幅に減少する。ドラッカーもこの点には気づいている。
現在一般的となっている組織構造では、膨大な数の中間管理職がトップの予備軍となり、トップになるための準備を行ない、テストされている。その結果、マネジメントの上層部にいつ欠員ができても、選考の対象となる人はつねに大勢いるようになっている。しかし情報化組織において、マネジメントのポストが大幅に減少した後、トップはいったいどこから来ることになるのか。トップとなる人たちにどこで準備をさせるか。どのようにテストするか。だが、ドラッカーは依然として分権化の利点を捨てていない。組織はフラット化するが、同時に分権化も行う。そして、前回の記事「【ドラッカー書評(再)】『新しい現実』―組織の目的は単一でなくてもよいのではないか?という問題提起」でも書いたように、組織の目的は単一でなければならない。これらの条件を同時に満たせるのは、企業が単一の(もしくはごくごく限定的な種類の)製品・サービスをグローバルに展開する場合ではないだろうか?トップマネジメントの下には、世界の各エリアを担当するミドルマネジメントが存在し、彼らに対して分権化を行う。ただし、ミドルマネジメントはせいぜい1階層にとどまる。その下にはすぐに一般社員が配置される。
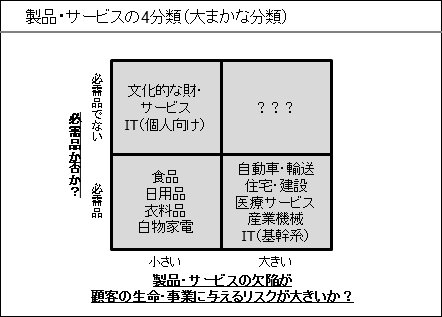
またこの図を使うことをご容赦いただきたい(何度も言い訳をして申し訳ないが、未完成である。図の説明については、以前の記事「森本あんり『反知性主義―アメリカが生んだ「熱病」の正体』―私のアメリカ企業戦略論は反知性主義で大体説明がついた、他」などを参照)。ドラッカーが想定しているであろう組織は、上図の左上の象限においてよく機能する。
左上の象限はイノベーションによって世界市場を席巻する場合であり、アメリカ企業が得意とする。アメリカのイノベーターは、イノベーションを世界に普及させる際、各国の事情に合わせてカスタマイズしようとは考えない。そんなことをしていては経営のスピードが落ちる。それよりも、必ずしも必需品ではないそのイノベーションを、世界中の人が心の底からほしがるように、プロモーションに多大な投資をする。そして、言葉は悪いが、イノベーターが考案した単一のイノベーションを、全世界の人々に”押しつける”。そうすることで、世界の市場シェアを一気に獲得する。
一方、日本企業が強いのは右下の象限である。右下の象限は、必需品である上に顧客ニーズが多様化しており、難易度の低い製品・サービスから難易度の高いものまで、多様なラインナップを揃える必要がある。そのため、新入社員はまずは簡単な製品・サービスを担当し、長い時間をかけて難しい製品・サービスを担当できるように訓練される。この考え方は現場社員だけでなくマネジャーにもあてはまる。したがって、日本企業は階層が非常に多い組織となる。
実際、アメリカから組織のフラット化というコンセプトが輸入されても、日本企業はフラット化するどころか、管理職の割合がむしろ増えたぐらいだ(以前の記事「【ドラッカー書評(再)】『現代の経営(上)』―実はフラット化していなかった日本企業」を参照)。そしてこの傾向は、日本の社会が多層化されていた方が全体として安定するという伝統と合致する(以前の記事「山本七平『山本七平の日本の歴史(上)』(2)―権力構造を多重化することで安定を図る日本人」を参照)。
ちなみに、左下の象限にも多くの日本企業が存在する。しかし、左下の象限に該当する組織の多くは、右下の象限のように多くの階層を抱えることができない。飲食店で店長とスタッフの間に4つも階層を設けることは不可能である。階層が少ないがゆえに、若手社員はすぐにキャリアの限界に達してしまい、それが早期の離職へとつながる。若手社員の離職率が高いと、企業は不安定になる。こうした問題を解決する方法として考えられるのは、1つには川上へと進出することである。小売業であれば、製品を自社開発する。できれば製造まで自社で手がける。もう1つは異業種に進出して多角化し、社員のキャリアパスを多様化させることである。
(5)
日本株式会社は、今日にいたるも世界中を畏怖させている。しかし実際には、日本で機能したのは計画ではなかった。日本でも計画は、ソ連流計画や社会主義計画と同じようにほぼ失敗だった。実際のところ、日本の政府は間違った計画を立ててきたにすぎない。成功した産業のうち、政府計画によるものはほとんどない。自動車、民生用電子機器、カメラの成功は、政府計画によるものではなかった。むしろ、これら3つの産業は政府に邪魔されていた。日本経済が戦後に急成長を遂げたのは、かつての通商産業省が財界をリードして、官民一体となって輸出を進めたからだとする説がある。ドラッカーはこの説を否定する。また、マイケル・ポーターも、著書『日本の競争戦略』の中で、この説が誤りであることを詳細に解説している。
 | 日本の競争戦略 マイケル・E. ポーター 竹内 弘高 Michael E. Porter ダイヤモンド社 2000-04 Amazonで詳しく見る by G-Tools |
私の考えでは、それでも政府計画は不可欠である。政府計画に唯々諾々と従うだけの産業や企業は衰退する。一方で、政府計画に対して、「計画通りにやってみたが、どうやら現実はこうなっているようだ。だからこれをやらせてほしい」と「下剋上」をした産業や企業は成長する。こういうことなのだろうと思う(以前の記事「山本七平『帝王学―「貞観政要」の読み方』―階層社会における「下剋上」と「下問」」を参照)。
初めから修正・否定されることが解っている政府計画なら、作らなければよいのではないかと感じるかもしれない。しかし、日本人は伝統的に外圧がないと積極的に動かない集団である。「皆さんに任せた。皆さん、自由に考えてくださって結構です」と上から丸投げされても、その自由の扱い方を日本人は知らない。よって、きっかけとしての政府計画は必要である(そして、その政府計画を立案する政府/行政もまた、何かしらの外圧に突き動かされている)。
ブログ別館の記事「『アベノミクス破綻(『世界』2016年4月号)』」でも少し書いたが、失敗するまちづくりは、国や都道府県が立てた計画をそれぞれの市町村がそのまま鵜呑みにしている。現場の実情をよく知らない国や都道府県が作った計画通りに箱モノを建設しては、毎年巨額の赤字を垂れ流す。まちづくりにおいては、市町村側の「下剋上」がもっと必要である。マスコミは国や都道府県が”ろくでもない”計画を作ったことばかりを批判する。しかし、本当に批判されるべきなのは、その計画に下剋上を挑まなかった市町村側の受動的な姿勢である。
企業の世界に目を向けると、日の丸半導体の象徴であったエルピーダが経営破綻したのは、産活法(2014年1月20日付けで、産業競争力強化法の施行に伴って廃止)によって「DRAMで世界一になる」という狭い縛りを経済産業省からかけられていたことも一因ではないかと私は考えている。変化の激しい半導体業界において、もっと柔軟に戦略を変更し、DRAM以外の分野にも挑戦する、といったことができていれば、経営破綻は避けられたかもしれない。
日本人にとって計画は必要悪である。計画はほぼ間違いなくその通りにならない。しかし、計画があるからこそ例外を識別できる。予期せぬ成功を呼び込むことができる。そして、予期せぬ成功に傾倒すると、計画が想定していた成果よりもはるかに大きな成果をもたらす可能性がある。「計画上は失敗だが、実際には成功した」―これが日本において最も望ましい(以前の記事「『人事再生(『一橋ビジネスレビュー』2016年SUM.64巻1号)』―標準化しなければ例外は発見できない、他」では、一橋大学の研究がマネジャーの「情報伝達」機能(ビジョン、戦略、計画を部下に伝える機能)を重視し、「例外処理」機能を軽視しているのではないかと指摘した)。
現在、安倍内閣は「地方創生」を掲げている。だが、肝心の地方創生計画の中身は地方自治体に任せきりにしているようで、危ない兆候だと感じる。その結果どうなるかは容易に想像がつく。どの地方自治体も、他の自治体の計画を真似するのである。そういう事態を避けるには、まずは国が「この地域ではこういう方向で地域活性化をさせよう」と、ある程度の計画を用意しなければならない。その上で、各地方自治体は、決してその計画に盲従するのではなく、「我々の自治体の現実はこうだ。だから、本当に必要な施策はこれだ」と「下剋上」する。国と地方自治体が主従関係に収まるのではなく、激しいつばぜり合いを繰り広げることが地方創生の要である。
カテゴリ:
┗ドラッカー書評(再)
,
経営








